9月1日は「防災の日」です
防災の日は、1923年9月1日に発生した関東大震災に由来しています。
この災害を人々の記憶に残し、防災意識を保っていくという目的で毎年9月1日を「防災の日」として制定されました。
また、「防災の日」を含む8月30日から9月5日までの期間は「防災週間」になります。
この期間に改めて、家庭で災害について考えてみましょう。
地震に注意しましょう!
現在、全国的に南海トラフ地震の注意や備えが叫ばれていますが、志免町を含む福岡都市圏では、警固断層帯への注意や備えも必要です。警固断層帯は、過去の活動と同様に北西部と南東部の2つの区間に分かれて活動すると推定されています。
過去の活動
警固断層帯(北西部)の最新の活動は、2005年の福岡県西方沖の地震(マグニチュード7.0)です。この地震以前の活動履歴は不明です。
将来の活動
警固断層帯(南東部)ではマグニチュード7.2程度の地震が発生すると推定され、今後30年の間に地震が発生する可能性が0.3%~6%と、主な活断層の中では高いグループに属することになります。
注意や備え
地震はいつ起こるか分かりません。日ごろからの地震の備えとして、普段から防災ハザードマップなどで、揺れやすさマップや地震発生時の注意点などを確認しておきましょう。
風水害に注意しましょう!
台風は、30年間(1991~2020年)の平均では、発生・接近・上陸ともに、7月から10月にかけて最も多くなります。
特に、8月と9月は日本に接近する台風が多く、このとき秋雨前線の活動を活発にして大雨を降らせることもあります。
また、台風の接近や通過時の暴風や大雨だけではなく、土砂災害や高潮などを引き起こす可能性もあります。
注意や備え
台風の情報を天気予報やネットニュースなどから入手し、普段から防災ハザードマップなどで、洪水や高潮のリスクなどを確認しておきましょう。
災害に備えましょう!
防災の基本は自助・共助(地域の防災力)です。
自分の身は自分で守る「自助」を防災の基本的考えとし、お互いに助け合う「共助」で地域を守ることに取り組めるよう、日頃から災害に備えておきましょう。
家庭で防災ルールを決めておきましょう
災害は家族が一緒にいる時に起こるとは限りません。いざという時に慌てず行動できるように、どこに逃げるのか、どこで待ち合わせをするのかなど、事前に家族で決めておきましょう。

備蓄品を準備しておきましょう
いつ起こるかわからない災害に備えて、食品は最低3日分、できれば1週間分を備蓄しておきましょう。
また、無理なく備蓄をしたい方は、「ローリングストック」がお勧めです!
「ローリングストック」とは、ふだん食べている食料品や日用品を多めに買っておき、使用した分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の備蓄を自宅に確保しておく方法をいいます。


家具の転倒防止対策をしておきましょう
地震が起こった際、負傷の多くは家具類の転倒・落下が原因です。転倒・落下した家具に挟まれたり、家具が倒れた時に割れた食器やガラスなどが、多くの負傷原因となります。
対策として次の事柄を実践しましょう。
(1) 家具の倒れる向きを考えて配置する
(2) 寝室には家具を置かない
(3) 家具を置く場合には固定器具で固定する
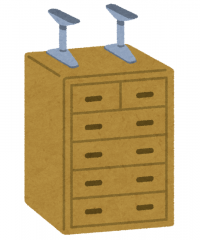
防災情報を確認しましょう!
災害が発生するおそれがある場合、新聞・TV・ラジオ・SNSなど様々な媒体から情報が発信されます。
また、以下のとおり防災情報の取得も可能です。有事に備え、ご確認・ご登録をお願いします。
○気象庁の防災情報・気象情報<外部リンク> (気象庁が発表する防災・気象情報を確認できます)
○福岡県防災ホームページ<外部リンク> (災害・避難情報や、災害の備えなどを確認できます)
○ふくおかけん防災ナビ・まもるくん<外部リンク>(災害時の情報をスマホやタブレットにお知らせします)※登録が必要です
○志免町防災気象情報システム<外部リンク> (宇美川の水位や三郡山の雨量などが確認できます)
○志免町公式LINE (避難所の情報や防災情報が確認できます)※登録が必要です
防災ハザードマップの活用
防災ハザードマップを活用し、お住まい付近の災害リスクや危険箇所、避難経路などの確認をしましょう。
ご自宅や勤務先などから安全な避難経路、避難所を確認し、すぐに安全な場所に避難できるよう防災意識を高めましょう。
※防災ハザードマップは、洪水・土砂災害・高潮・地震・火災への対応などの情報を掲載しています
危険を感じたらすぐ避難!
災害が発生するおそれがあるとき、状況に応じて避難できるよう5段階の警戒レベル<外部リンク>に応じた避難行動をとりましょう。
町から警戒レベル4(避難指示)や警戒レベル3(高齢者等避難)が発令された際には、速やかに避難行動をとってください。
避難指示等が発令されていなくてもキキクル(危険度分布)<外部リンク>などを用いて自ら避難の判断できるよう心がけましょう。
避難とは、指定避難所へ避難するだけではありません。川や崖から少しでも離れた場所や、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることも方法の一つです。